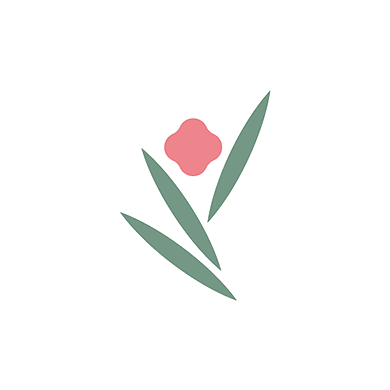福祉心理学科
福祉学部/4年制(入学定員/70名)
学科TOPICS
-
[福祉心理学科]令和7年度福祉心理学科学友会のシンボルマークが完成しました!
福島学院大学には学生による自治組織「学友会」があります。 全学学友会とは別に、各学科で構成される組織があり、年度ごとに役員の学生が選出されま…
-
[福祉心理学科]医療機関・福祉事業所就職説明会を実施しました。
4月18日(金) 社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得を目指し就職活動を行う4年生を対象に医療機関・福祉事業所就職説明会を行いました。 今年…
-
4月24日 福島駅前キャンパス 2月下旬から福祉心理学科学友会が企画と準備を進めてきた、『新入生歓迎会』を開催致しました! ボードゲーム、大…
どうして“福祉”と“心理”を学ぶの?
心のケアのできる
福祉と心理のスペシャリストに
福祉心理学科では、「福祉」と「心理」をバランス良く学んで、「心のケアのできる福祉と心理の専門家」を目指します。
福祉とは
「ひとのしあわせ」や「よりよく生きる」をお手伝い
相手の声に耳を傾け、そのひとにとっての「しあわせ」や、「より良い生き方」を一緒に考えていくことが「福祉」につながっています。
例えば「相談援助」も福祉のひとつの在り方ですが、「相手が弱者だから救済する」のではなく、相手にとっての「しあわせ」と「その人らしい生き方」を一緒に考えていく中で選択肢を共に探し出し、ご本人にどうしたいのかを決めて頂くお手伝いをします。また、互いにとって暮らしやすい町づくりに向けて、地域にも働きかけます。
心理とは
「ひとの心の働き」を考える
いじめ、虐待、引きこもり、学習障害、社会からの孤立などで「心の痛み」を抱えるひとを支援するには、「福祉」に加えて「ひとの心の痛み」に共感できなければいけません。
心理学はSF映画等の影響で、相手の心を見通したりできるイメージがあるかもしれませんが、実際には様々な手法で相手の行動を調査し、感情や記憶といった、目には見えない心の働きを科学する、非常に幅広い学問です。
働くためにはどんなスキルが必要?
現場で重要なのは「対人援助」のスキル
福祉というと「高齢者介護」や「障がい者支援」をイメージする方が多いのですが、実際にはその支援対象は多岐にわたります。福祉心理学科の目指す「対人援助職(ソーシャルワーカー)」とは、生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会の中で疎外されている人々に対して相談援助を提供する専門職です。
教育における「いじめ」や「ひきこもり」、家庭における「虐待」や「DV(ドメスティック・バイオレンス/家庭内暴力)」、地域社会の抱える「高齢者の孤立」などの問題はもちろん、大規模災害の被災者支援や、最新のIT機器が引き起こすテクノストレスなど、人々の抱える「心の問題」に寄り添い、心のケアのできる福祉と心理の専門家が求められています。


教育研究上の目的
福祉学部福祉心理学科においては、社会福祉、精神保健福祉、臨床心理、カウンセリング等の分野において将来の専門職として必要な教育を行うとともに、他者の心の痛みに共感でき、心の痛みを抱える人々に積極的な援助活動を行うことができる人材を育成する。
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
福祉心理学科の教育研究上の目的に基づき。福祉心理学科教育課程における学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、福島学院大学学則に定める卒業に必要な要件を満たした者に対して卒業を認定し、「学士(福祉心理学)」の学位を授与します。
教育課程の編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
福祉心理学科は、社会福祉、精神保健福祉、臨床心理、カウンセリング等の分野において、卒業認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、体系的教育編成を構築しています。
【卒業認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
●すべての学生が根拠に基づく(エビデンスベース)思考力と総合力を身につけるための、充実した教養教育の編成。 ●演習・ゼミナールや学生参加型対話型教育(アクティブラーニング)などの双方向型授業を主体とし、フィールドワークも活用したプロジェクト型の教育を通して、問題発見・解決力、構想・構築力・コミュニケーション力、実践力を培う専門教育の編成。 ●教養教育と専門教育における学生の主体的学びを構築するために、学問分野・レベル・授業形態などをカリキュラムマップ・カリキュラムツリー・ナンバリングなどによって体系化。 ●学生の自学自修による体系的な学びを、学修ポートフォリオなどによって可視化(みえる化)。【2つに大別される科目およびプログラム】
カリキュラムは、教養教育科目・専門教育科目に大別され、そこに関連する分野の科目によって、卒業認定・学位授与のための体系的学習が可能です。
①教養教育科目 ●広い視野に立ち、学士力の基礎となる基本的な教養(アカデミック・ツール)を提供する。 ●1~2年次の初年次教育によって、リテラシー(読む・書く・話す)および情報リテラシーを修得する。 ②専門教育科目 ●1~4年次までの専門教育科目によって、研究能力、専門的職業能力を育成するとともに資格取得のために高い知識・技能の修得を提供する。 ●学外実習や地域ボランティア活動を通して、地域と社会で実践的に学び、また貢献する機会を提供する。【成績評価の可視化 (みえる化)】
●教育課程レベルや科目レベルでの「学修成果の評価方針(アセスメント・ポリシー)」を踏まえて行う。入学に関する基本的な方針(アドミッション・ポリシー)
建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity(真心=偽りや飾りのない心)とHospitality(思いやり)の体得に努め、探求心を持って地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持ち、卒業の認定に関する方針(ディプロマ・ポリシー)及び教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力を備えた将来、対人援助職を目指す人を募集します。
【入学前に身につける能力・素養】
①知識・技能高等学校までの履修内容について、科目の偏りがなく総合的に身につけている。
②思考力・判断力・表現力などの能力
(1)現代社会に関心をもち、物事を筋道立てて考えることができる。
(2)課題やテーマについて調べ、分かったことや気づいたことを他者に伝えることができる。
③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
(1)自分の目標を持って意欲的に学ぶことができる。
(2)他者を尊重することができる。
(3)他者と協力して課題に取り組むことができる。
【入学選抜の方針】
●入学選抜では、福祉心理学科で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。 ●入学後の学修の基礎となる知識・技能、論理的思考力、判断力・表現力、および主体性・協働性(学力の三要素)を入学者選抜において確認する。【評価方法】
●「入学前に身につける能力・素養」を、福祉心理学科の入学者選抜において評価する。「学科の魅力」を見る