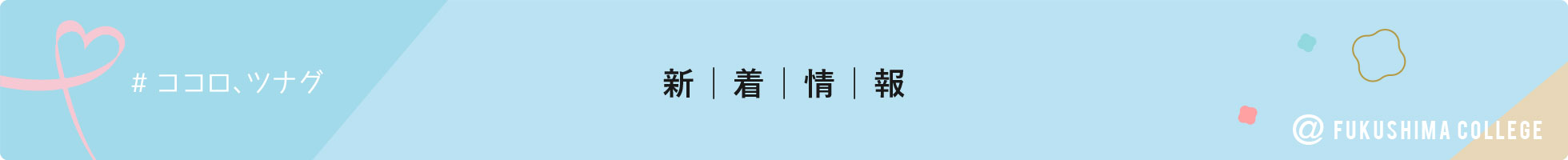
[食物栄養学科]1年生「調理学実習」行事食献立の実習その②
1年次調理学実習最後の実践授業
行事食第3回目は前回に引き続き、正月料理。
これまで学んできた基礎をフルにいかしながら、華やかにアレンジされた正月料理に挑戦しました。
低温調理の技法をいかしコールドビーフに挑戦
低温調理とは、食中毒菌が不活性化する一定の低温で加熱状態を保つことにより、肉本来のうまみをのがさず、食味をよくする技法です。
栄養士の知識には欠かせない「安全に美味しく食べられる」調理法を学びました。
先生の実演と同時に、各班の代表者が下準備を開始。



班員が自然にフォローに入ります。
下味をつけた後、たこ糸で形を整え、蒸し器へ。
様々な調理法がある中、他料理の工程を考慮し、蒸し器での調理をおこないました。
調理器具・機器を状況に応じて使い分けることは、栄養士として必要なスキルです。

「口取り」の「伊達巻き」を手作り
「口取り(くちとり)」とは、おせち料理の祝い肴のひとつ。
宴席の最初に提供する「口取り肴」を略した言葉と言われています。
栗きんとん、錦玉子、紅白かまぼこ等がこれにあたり、正月らしい華やかな色彩と縁起が良いとされる食材を使用します。
今回は、橋本先生の特別レシピで伊達巻きを作成しました。



伊達巻きに使用する「鬼すだれ」。
通常の巻簾と異なり、竹が三角の山型になっており、伊達巻き特有のすじをつくることができます。
巻き寿司の回で学んだ巻簾の取扱方法を振り返りながら説明がおこなわれました。

その他、「自宅で再現したいがオーブンがない」といった学生むけに卵焼き器を使用する方法も紹介されました。
実践の様子
調理する品数・作業工程が多い中、各班とも分担しながら調理を進めていきます。




かまぼこの飾り切りに挑戦。

茹で卵(卵黄)の裏ごしに挑戦。十字マス目の向きに対し斜め45度を意識。
隣では、お雑煮用の結び三つ葉を準備しています。

焼き上がった伊達巻きは、巻きやすいよう切れ目を入れてから巻いていきます。



飾り切り、鬼すだれの使い方、種類が異なる海老の処理方法等々、今回の実習では、「難しい」の声が飛び交っていました。
教職員もできる限りフォローに入り、直接指導をおこないます。



完成
本日の献立
・お雑煮(かつお節と昆布、鶏肉を出汁に使ったすまし仕立て)
・アボカドと魚介の前菜
・赤海老のテルミドール風グラタン
・伊達巻き(海老入り)
・コールドビーフ 温野菜添え(焼きトマト、ブロッコリー)

各班とも素晴らしい仕上がりです。





最後に、お雑煮の出汁が上手にできて満足げなショット。

































